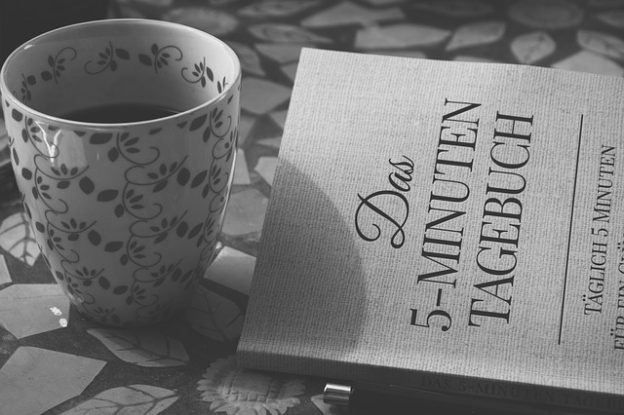本ページはプロモーションが含まれています。
「その人らしさの尊重」は
「よい看護」の必須条件?
看護・医療領域の出版に携わる関係から、病院の看護部・看護局のホームページによくアクセスするのですが、そのたびに気になることがあります。「看護部の理念」「看護局の理念」として書かれているなかに「その人らしさを尊重する看護を提供します」との一文をあげている看護部や看護局が実に多いのです。
この「その人らしさを尊重する」という表現は、看護の研究論文のタイトルなどでもよく使われています。また、看護職や看護教員の方を取材していても、話のなかにこのフレーズがよく登場します。
最近では、ICF*の考え方が普及している介護や福祉の領域でも、「その人らしい生活」とか「その人らしさを取り戻す」という表現が好んで使われているようです。
「その人らしさ」の理解
「その人らしさを尊重する」という文言が「よい看護」「よいケア」のキャッチフレーズのように安易に使われている感がないわけではありません。
看護師のあなたは、そもそもこの「その人らしさ」という言葉にどのような思いを込め、どのような意味合いで日々使っていますか。また、患者個々の「その人らしさ」をいかに把握し、理解して、具体的な看護につなげておられるのでしょうか。
看護における
「その人らしさ」の定義は?
慢性疾患看護専門看護師の下村晃子さんも著書*¹のなかで、この「その人らしさ」「その人らしい」ということに繰り返し言及しておられます。
たとえば、冒頭の「序に変えて」のなかで下村さんは、四半世紀を超える間、脳神経系疾患の患者や家族にかかわってこられたことを紹介。そのうえで、その長い間一度もぶれることなく「その人らしい生活を取り戻す手助けをしたい」という思いのもとに看護に取り組んできた、と記しておられます。
続いて、この「その人らしい」とか「その人らしさ」という言葉を、こんなふうに定義しています。その人の価値観や人生観など、「その患者個人を特徴づけているものであり、その人がこだわっている生き方のスタイルそのもの」だと――。
ちなみに、ここで言う「こだわり」の理解、そしてその探り方については、「その人らしさ」は「その人のこだわり」からをあわせてご覧ください。
認知症ケアで重視される
「パーソンフッド(その人らしさ)」
認知症ケアの領域にも、「その人らしさ」を重視する根拠らしきものはありました。
1990年代初頭に英国の臨床心理学者、トム・キットウッド(T. Kitwood)が、「パーソンセンタード・ケア」という概念を提唱しています。この概念は、あまり時間を置かず日本に紹介され、認知症ケアの専門職を中心に、一時期かなりのブームになりました。
この概念について、認知症介護研究・研修東京センターのセンター長を務めておられた当時の長谷川和夫医師を取材させていただいたことがあります。老年精神医学者で、あの認知症スケールの開発者である長谷川医師です
その人の言いなりになることではない
そのとき長谷川医師は、キットウッド博士の著書『Dementia Reconsidered』の中心概念が「パーソンフッド(Personhood)」であるとし、「これを日本語でいえば、”その人らしさ”ですね」と説明してくれました。
そのうえで、パーソンセンタード・ケアは、「認知症者の言いなりになることではない。もちろんケアする側の都合を優先することでもありません」と説明してくれたことを印象深く記憶しています。長谷川医師のこの説に関心のある方は、『その人を中心にした認知症ケア―みんなで学ぼう』(ぱーそん書房)が参考になります。
「その人らしさ」を
看護として理解するには
看護の場面でも介護場面でも、「その人らしさ」ということを意識しすぎると、長谷川医師が指摘されたように、とかく「患者の言いなり」になってしまうのではないでしょうか。それを避けるために大切なこととして、下村さんは先の著書で以下をあげています。
- 患者との言語的・非言語的コミュニケーションを通して、
- 「その人がこだわっているもの」「それにこだわる理由」を知るとともに、
- 「その人の強み」、つまり「その人が今持っている力」「自分でできること」についても理解する
つまり、患者個々が今持っている力を最大限発揮して、日常生活に自分らしさを取り戻し、主体的に生活していけるように支援すること――。このことが、その人らしさを尊重することにつながっていくのだろうと、私なりに理解したところです。
「その人らしさ」を知るヒントがその人の「嗜好品」に
なお、看護師さん同様、医師たちもまた、日々の診療場面において患者個々の「その人らしさの尊重」には力を入れています。その典型例として、「嗜好品外来」というユニークな外来があることをご存知でしょうか。
患者に自分の嗜好品について話してもらうことをきっかけに、趣味について、こだわっていることについて……、と話を進めていく――。このことが、対面している患者のその人らしさを知ることにつながっていき、治療やケアに役だつのではないでしょうか。詳しくは、「看護師は患者の嗜好品にも関心を」を参考にしていただけたら嬉しいです。
参考資料*¹:下村晃子著『生活の再構築―脳卒中からの復活を支える (SERIES.看護のエスプリ)』(仲村書林)