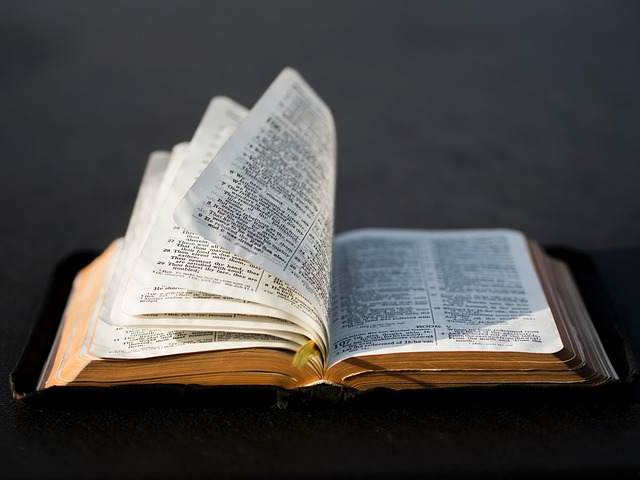患者が日本人でも
宗教的配慮は欠かせない
この先ますます増加が予測される訪日外国人――。医療機関が彼らを患者として受け入れて医療行為を行う際には、宗教や習慣などに配慮して特別な対応が求められることが少なからずあることは言うまでもないでしょう。
しかし、患者の信仰上の理由や倫理観、価値観の相違などにより、救命や健康維持の観点から医療者サイドが勧める医療行為や看護ケアに患者が拒否の姿勢を示す場合があるのは、何も外国人に限ったことではありません。
日本人の宗教について言えば、「宗教を信じるか」の問いに74%の人が信仰を「もっていない、信じていない、関心がない」と回答したとする統計データがあります(統計数理研究所「2018年 国民性調査」による)。
この結果が示すように、日本人には無宗教の人が圧倒的に多いものの、逆に言えば26%、つまり4人に1人余りの日本人は何らかの宗教をもっているわけです。ですから、医療行為や看護ケアにおいて患者個々の信仰心、宗教観に配慮が求められるケースは少なくないと言えるのではないでしょうか。ということで、今回はその辺の話を書いてみたいと思います。
「エホバの証人」信者が
信仰を理由に輸血を拒否
宗教的配慮が求められるケースの代表と言えるのが、「エホバの証人と輸血」の問題です。キリスト教系の新宗教として知られる「エホバの証人」の信者は、日本国内だけでも21万6472人いる(「2019年エホバの証人の年鑑」による)とされています。
信者数の多さと、日本支部が全国各地に点在していることから考えても、救命の観点から輸血が必要なものの患者から信仰を理由に輸血を拒否されるという事態は、どこの医療機関でも直面しうる問題と思われます。
実際、現場の医師を対象にした直近の調査で、69.8%の医師が患者に輸血を拒否された経験をもち、42.3%は複数回経験していると回答していることが報告されています(日経メディカルonline2023年4月28日)。
輸血拒否の解釈に信者間で幅がある
この、エホバの証人の信者による輸血拒否に関しては、日本医師会のホームページで、東京医科歯科大学生命倫理研究センター、センター長の吉田雅幸医師らが「エホバの証人と輸血」と題し、対応策を簡潔に明示しています*¹。
そこではまず、「エホバの証人の信者」と一口に言っても、実際に輸血に関する考え方には微妙な個人差があり、大きく「絶対的無輸血の場合」と「相対的無輸血の場合」とに分けられる、と説明しています。
「絶対的無輸血の場合」とは、輸血をしないと生命の危機に陥るリスクがあることを伝えても、頑として輸血を拒否するケースです。
一方の「相対的無輸血の場合」は、輸血をしなくても生命の危機や重篤な障害に至るリスクがないと判断される場合に限り、輸血を拒否するケースです。
医療現場で実際に問題になるのは前者。つまり、たとえ自分の命を落とすことになっても輸血は受けられない、というケースです。
このことは、エホバの証人の信者である患者を前にしたら、輸血を受けることについてその都度本人の意思確認を行う必要があることを示唆しています。
エホバの証人輸血拒否への
医療機関としての方針を周知
エホバの信者である患者から信仰上の理由で輸血を拒否される場面として、吉田医師らは以下の3ケースをあげ、個々について医療者サイドがとるべき対応を明示しています。
待機的手術における輸血拒否への対応
手術に際し、手術中に救命のために輸血が必要になることが予測される場合は、術前に以下の選択肢を提示して患者の意思決定を促す。
- 輸血が必要になれば輸血することを事前に伝えて患者に自己決定する機会を与え、患者が拒否した場合は治療を断る。
- 患者の意思を尊重し、その意思を書類に明記してもらったうえで無輸血下に手術を行う。この手術により、仮に患者が出血死する事態になっても、その意思表示書があれば医療機関側が責任を問われることはない。
救急医療など緊急時における輸血拒否への対応
事前に患者の意思を確認できない状況下で緊急的処置として輸血が必要になる事態に備え、事前策として、医療機関としての対応について方針を策定しておく。
さらにその策定内容を「宗教上(エホバの証人)の理由による輸血拒否への対応について」として院内掲示、あるいは病院のホームページなどさまざまな手段を活用して公開し、患者や地域住民への周知を徹底する。
未成年者や意思確認できない患者の親権者などによる輸血拒否への対応
未成年の患児、あるいは自己決定能力がない患者で、その親権者や家族が信仰上の理由により患児・患者への輸血を拒否する場合は、医療機関としての方針を説明し、方針に同意が得られないときは転院を勧める。
なお、この問題については、2008年2月に日本輸血・細胞治療学会、日本麻酔学会、日本外科学会など関連学会の合同委員会が報告した「宗教的輸血拒否に関するガイドライン」*²が参考になります。
ちなみに本ガイドラインは、親権者が15歳未満の子どもへの輸血を拒否した場合、「医療者側は親権者の理解を得られるように努力し、なるべく無輸血治療を行うが、最終的に輸血が必要になれば、輸血を行う」としています。
また、厚生労働省は2022年12月に全国の自治体などに宛てて発出した通知*³で、「医師が必要と判断した医療行為(輸血等)を行わせない」ことはネグレクト(育児放棄)に該当するとしています。
日常的な看護ケアにおいて
宗教的配慮をしていますか
医療行為そのものとは別に、看護ケアにおいても宗教的配慮が求められることもあります。この点については、日常的な看護ケアにおいて宗教的配慮がなされている実態を明らかにすることを目的にまとめられた、甲斐ゆりあ氏ら研究チームによる論文*⁴があります。
この研究でとり上げているのは、全世界の人口の約7割を占めるとされる3大宗教、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教です。個々の宗教について、信者に対する看護ケアにおいて宗教的配慮が求められる22項目*をピックアップし、その配慮を踏まえたケアが行われているかどうかWeb調査を行っています。
①礼拝のための「祈禱室がある」、②亡くなられた際のケア、③出棺の際の旅立ちのための準備など、具体的にあげられている。
調査の対象とされたのは、訪日外国人患者が多いと推定される首都圏にある300床以上の医療機関18施設の看護管理者です。調査対象が限定的ですが、実施されている宗教的配慮が具体的に明記されている点に、個人的には大変興味をもって読ませていただきました。
6割以上の施設で実施されている食事への宗教的配慮
たとえば、特別な食事を必要とする宗教に対する食事の提供は、6割以上の施設で実施されているとのこと。ただし礼拝のためのスペース確保など環境面で配慮しているのは、2~5割と施設により差があること等が紹介されています。
世界的に信者が多いということは、日本人の信者も少なくないことを意味します。それだけに、対外国人患者だけでなく日本人の患者ケアにおいても、宗教的配慮が求められる話ではないかとの思いから、紹介させていただきました。
宗教や信条による食事の制約を知る
なお、宗教や信条による食事の制約は、配慮が欠かせない最も基本的な項目です。この点については、本人に直接確認するのが確実ですが、東京都がまとめている「外国人おもてなしポイント」*⁵なども参考になるのではないでしょうか。
ここでは、イスラム教、仏教、キリスト教、ヒンドゥー教に加え、ベジタリアンの患者への食に求められる配慮を理解することができます。
参考資料*¹:日本医師会「エホバの証人と輸血」
参考資料*²:宗教的輸血拒否に関するガイドライン
参考資料*³:令和4年12月27日 厚生労働省子ども家庭局長通知「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」
参考資料*⁴:甲斐ゆりあ・安藤敬子・清村紀子:日本の看護ケアにおける宗教的配慮の現状に関する実態調査、看護科学研究 vol.17,22-27(2019)
参考資料*⁵:東京都「外国人おもてなしポイント 宗教別・信念」