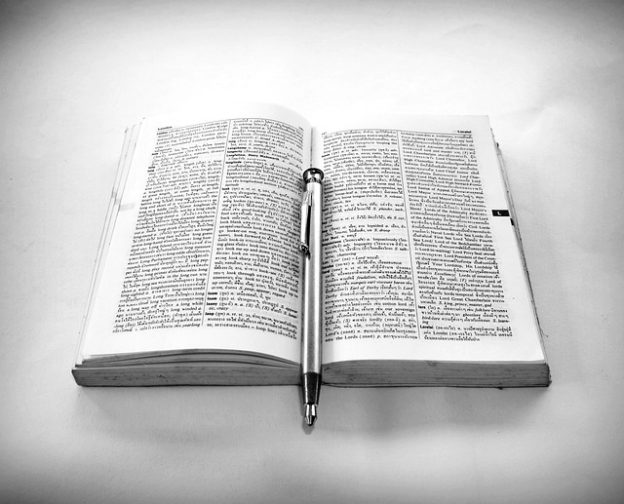本ページはプロモーションが含まれています。
「ナイチンゲール看護」に
立ち返ってみよう
近代看護の礎を築き上げたフローレンス・ナイチンゲールが、看護の基本を『Notes on Nursing(看護覚え書)』としてまとめ上げ、その初版が刊行されたのは、1860年でした。以来、160年を優に超えた今もなお、この覚え書は、世界のあらゆる地で看護実践の拠り所として愛読され、活用されているようです。
看護の現場を取材させていただくなかで私も、これらの著作に収められているナイチンゲールのたくさんの教えが、さまざまなかたちとなって日々の看護に、さらには医学や福祉の領域での実践などにも生かされている現実を、数多く目撃してきました。
というわけで、今回はナイチンゲール看護についてこれまで目にし、耳にしてきたことのなかで、とりわけ印象深く残っていることを書いてみたいと思います。
看護は観察で始まり
患者との合点で終わる
わが国では、『看護覚え書』の英語版が出てから8年後の1968年4月、その日本語版が『看護覚え書ー看護であること看護でないこと』*¹となって刊行されています。
刊行から20年以上を経て、この本の翻訳メンバーのおひとりである薄井坦子先生を、当時教鞭をとっておられた千葉大学の教授室にお訪ねしたことがあります。そのときのインタビュー取材のテーマは、「看護観察」でした。
このテーマを選択したのは、ナイチンゲールが『看護覚え書』のなかの「病人の観察」の章において、「看護師に課す授業のなかで、最も重要でまた実践の役に立つもの」として「観察」をあげていることに、特に注目したのがきっかけでした。
観察することが目的ではない
看護を実践するための観察である
ナイチンゲールは、「看護とは、患者の生命力の消耗を最小にするよう生活過程を整えること」と定義しています。このフレーズを目にしたとき、ではそれをするために看護師は具体的に何をすべきなのだろうかという疑問が、当然ながら湧いてきました。
この答えを求めてさらに読み進めていき、観察について書かれている箇所にたどりつき、そこではじめて「なるほど」と納得させられたものです。
ナイチンゲールはその観察について、「観察することが目的になってはいけない」と書いています。観察して得た情報から、患者にとって最善と思われる看護の手立てを導き出し、患者を癒すことにつながらないような観察は役に立たない、とまで断言しているのです。
観察したことが看護に生きているか
長いインタビューの締めくくりとして薄井先生は、「ナイチンゲールが語っているように、観察することが目的ではない」としたうえで、こう話してくれたことを、その時の先生の満足げな表情とともに印象深く覚えています。
「要するに、看護は観察で始まり、患者との合点(がてん)によって終わるということです」
観察データのデジタル化、さらには医療を標準化したクリニカルパスの普及などにより、観察したことと看護の実践とがなかなかつながりにくい現状にあって、とても貴重な教えだと思うのですが、いかがでしょう。
⇒ クリニカルパスと看護の個別性(バリアンス)
ナイチンゲールがいち早く指摘した
「持てる力」への視点
ナイチンゲールは「観察すること」をすべての看護の起点として位置づけたわけですが、その観察において、何をどう見るかが、その後に続く看護実践の質に大きく影響します。アセスメントの視点次第で看護の良しあしが決まるということです。
この観察の視点に関して思わぬ方から、「実は今話題になっていることは、昨日今日の話ではない。あのナイチンゲール女史が1世紀以上も前に指摘していることです」と聞き、改めてナイチンゲールの存在の大きさを再認識させられたことがあります。
その「思わぬ方」とは、日本におけるリハビリテーション医学のオーソリティーであり、国際リハビリテーション医学会の会長なども務められた上田敏(さとし)医師です。「障害」というものの新たなとらえ方について取材させていただくなかでのお話でした。
「できないこと」ではなく「できること」に視点を
病気などによる障害のとらえ方について、WHO(世界保健機関)は2001年5月、人間の生活機能として「できること」に視点を置くことによって人の全体像を前向きに理解していこう、という考え方を公表しました。
障害の度合いを「できないこと」に視点を置いて捉えるというそれまでの方法をやめ、「できること」を見ていくという、まさに180度転換する方針を打ち出したわけです。そして発表されたのが、現行の「生活機能分類」(ICF)です。
ICFの考え方を受けてリハビリテーションは、そして看護も、「病気があるから〇〇ができない」と否定的にとらえるのではなく、「病気で制限されるけれど、こうすればできるよね」と肯定的にとらえ、その人の持てる力を最大限引き出し、なおかつその持てる力を高めるようにかかわっていこうと変わってきたのです。
この「できないことではなくできることに観察の視点を置く」こと、つまり「その人の持てる力に注目する」という発想を最初に言ったのはナイチンゲールだった。言い換えれば、WHOが発表した「ICF」構想のおおもとは、ナイチンゲールの健康観にあったということだと、上田医師は話してくれたのでした。
なお、ICFに関心のある方は、「ICFの発想で「できることを奪わない」看護を」をあわせてご覧ください。
その人の「持てる力」を引き出し、
その力を最大限生かすかかわり
取材を終えて帰宅した私は、上田医師から教えられた『ナイチンゲール著作集 第2巻』*²のなかの「病人の看護と健康を守る看護」と題する論文を読んでみました。
確かにそのなかでナイチンゲールは、「持てる力を充分に活用できている状態」を「健康」と定義しています。その健康観のうえに、その人の持てる力を引き出し、その力を最大限発揮できるように手助けすることが看護であるといった趣旨のことが書かれていました。
この「患者の持てる力を引き出す」という発想で日々の看護を実践している看護師さんは、慢性期看護の現場を中心に、少しずつですが、最近増えてきているように思います。あなたの職場ではいかがでしょうか。
生活の再構築を必要としない患者はいない
先に私は、仲間たちとのおしゃべり会で話題になったことをこちらの記事にまとめましたが読んでいただけましたでしょうか。この記事を読んでいただけると、より理解を深めていただけると思うのですが……。
⇒ 生活の再構築を必要としない患者はいるだろうか
いずれにしても、慢性期疾患は言うまでもなく急性期疾患であっても、医療を必要とする状態にいっときでも陥ると病前の生活にそのまま戻ることは難しく、大なり小なり生活を立て直すことが求められるものです。
その生活の再構築を余儀なくされている患者へのかかわりに欠かせないのが、ナイチンゲールの教えである「できること」への視点、そして「その人の持てる力を引き出し、その力を最大限生かせるようにかかわること」だろうと、改めて実感させられているところです。
なお、ナイチンゲールは統計学の優れた実践者としても広く知られています。詳しくはこちらを読んでみてください。
参考資料*¹:『看護覚え書(第8版) (看護であること看護でないこと)』(現代社)
2023年1月6日刊行の最新版である第8版は、50年以上にわたるナイチンゲール研究の蓄積が反映されていて、これまでの訳本にはない内容となっています。
参考資料*²:『ナイチンゲール著作集 第2巻』(現代社)