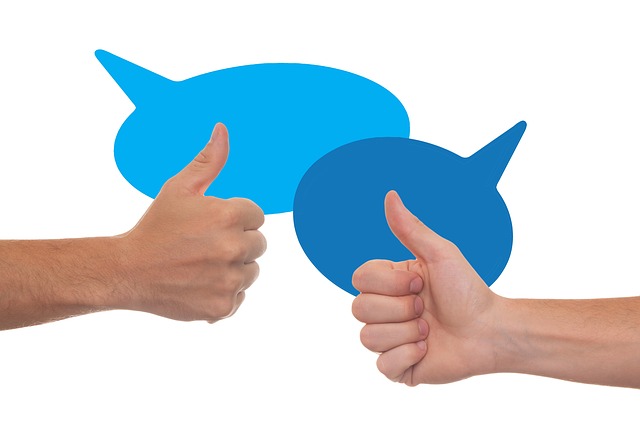本ページはプロモーションが含まれています。
ACP(人生会議)における対話は
シェアード・ディシジョンメイキングで
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)、いわゆる「人生会議」では、シェアード・ディシジョンメイキング(shared decision making:SDM)に基づいた対話を重ね、患者の意思(思い)に沿って話を進めていくことが重要と、よく言われます。
シェアード・ディシジョンメイキングをそのまま訳せば、「ディシジョンメイキング(意思決定)をシェア(共同)する」という意味になります。ビジネスの世界でも使われている言葉で、日本語では、「共同意思決定」あるいは「共有意思決定」の訳語で紹介されていることが多いようです。
医療現場で言えば、「医療を提供する側(医療従事者)と受ける側(患者)とが共同、つまり一緒に話し合って治療やケアに関する意思決定をする」となるでしょうか。
シェアード・ディシジョンメイキングは
インフォームド・コンセントから一歩前進
意思決定ということで言えば、日本の医療現場では、患者が受ける検査や治療については「すべて先生にお任せしますのでよろしくお願いします」「ではお任せください」といったことが無条件にまかり通る時代が長く続いてきました。
やがてインフォームド・コンセント、日本語では「説明と同意」ということが言われはじめました。医療者サイドが患者サイドに病状や治療方針を説明し、説明を受けた患者の「納得したうえでの同意」を得たうえで検査や治療を行う、ということが行われるようになったのです。
シェアード・ディシジョンメイキングは、このインフォームド・コンセントをさらに一歩進めた患者と医療者間のコミュニケーションスタイルとして、とりわけ最近は、ACPとのからみで関心が高まっているようです。
そこで今回は、ACPの取り組みに欠かせないとされるシェアード・ディシジョンメイキングについて、なぜACPにシェアード・ディシジョンメイキングが求められるのか、を中心に書いてみたいと思います。
シェアード・ディシジョンメイキングでは
エビデンスも治療目標も共有する
医療現場を取材するなかでシェアード・ディシジョンメイキングという言葉を見聞きするようになって、すでに10年余りになります。この言葉を初めて聞いてまず疑問に思ったのは、「患者と医療者が何をシェアして意思決定しようというのだろうか」ということでした。
この疑問については、ACPに関する取材のなかで、この言葉を口にされた何人かの医師や看護師さんに尋ねてみたり、種々文献を読んだりもしてみました。
患者の価値観や医療・ケアへの希望もシェアする
そのうえで私なりに、シェアード・ディシジョンメイキングをこう結論づけました。
治療方法に関するエビデンス(科学的根拠)はもちろんのこと、治療方針、患者の価値観や希望など、患者と医療者双方が持ち合わせているこの先の治療やケアに影響を与えるであろうあらゆる情報をシェアすること、だと――。
同時に、あらゆる情報をもとに設定する治療やケアの目標についても、患者と医療者が対話を重ねることを通してシェアし、一緒に考えて合意し、意思決定する――。
この一連の過程をシェアード・ディシジョンメイキングと呼んでいるわけです。さらに付け加えるなら、取材で答えてくれた方のなかには、次のように話してくれた医師もいました。「シェアード・ディシジョンメイキングに基づいて選択し、実施した治療やケアについては、その結果責任も、患者と我々医療者とが共有することになる」と――。
事前指示書とACPを分ける
シェアード・ディシジョンメイキング
一方でACPについては一般に、人生の最終段階、つまり終末期における医療やケアに限った話のように扱われがちです。しかし、そもそもACPは、終末期に限った話ではありません。この先提供される医療やケアが患者本人の意思にできるだけ沿うかたちで行われるように、医療者が患者との対話を重ね、思いや希望を伝えてもらうという取り組みです。
この場合患者側からすれば、自分が受けたい医療やケア、受けたくない医療やケアについて自身の思いや希望を伝えるだけなら、事前指示書やリビングウイルにその要望を書き記しておけばいいと考える人が少なくないようです。
患者の価値観に沿った医療・ケアを実現するために
しかし医療者サイドとしては、患者の病状との兼ね合いでみたときに、「患者が希望している治療やケアにはリスクがありすぎて、責任をもって希望どおりの治療やケアを行うことはできない」、と判断をせざるをえないこともあるでしょう。
あるいはその逆もありうるでしょう。つまり時として、「この患者の今の病状なら、患者が望んでいる生き方の支えになるようなこんな治療やケアの方法があるのに……」ということも間々あるはずです。
そこで、真に患者の価値観に沿った医療・ケアを実現するためには、一方通行になりがちなインフォームド・コンセントではなく、シェアード・ディシジョンメイキングに基づく患者と医療者の双方向での対話の積み重ねが必要になってくる、ということだろうと思います。
患者との共同作業に活用したい
新しいコミュニケーションスキル
少々ややこしい話になってしまいましたが、大筋はご理解いただけたでしょうか。さらに詳しく知りたい方には、『これから始める! シェアード・ディシジョンメイキング 新しい医療のコミュニケーション』*²という本をお勧めします。
この本を書かれた中山健夫教授(京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野)は、すでに2000年代の初めからシェアード・ディシジョンメイキングの普及に取り組んでおられます。本書の序文で中山教授は、シェアード・ディシジョンメイキングのめざすところを、次のように記しておられます。
「異なる立場にいる医療者と患者が、共有する問題に向き合い、お互いの立場・考え・価値観を少しずつ調整しながら、協力して調和できる解決策を探っていくことです」
(引用元:「これから始める! シェアード・ディシジョンメイキング 新しい医療のコミュニケーション
」*² 序文)
ACPだけでなく、さまざまなケア場面における患者との協働作業を考えるうえで、ヒント満載の一冊ですから、是非読んでみてください。
なお、2024年6月13日には、本書の改題改訂第2版『実践 シェアード・ディシジョンメイキング 改題改訂第2版』(医事新報社)が刊行されています。新たな実践症例が大幅に追加されていて、より実践的な内容になっています。
「シェアード・ディシジョンメイキング」の考え方やその支援については初心者で、もう少し手軽なところから入りたいという方には、中山和弘著『患者中心の意思決定支援―納得して決めるためのケア』*³がお勧めです。
ACP相談員(ファシリテーター)には必読書
また、ACP相談員(ACPのファシリテーター)を目指す方にこれらの本は、必読書でしょう。このACP相談員についてはこちらで詳しく紹介しています。是非読んでみてください。
メッセンジャーナースの活動も
なお、このところ地域を中心に対話を重視した活動が高く評価されているメッセンジャーナースの目指すところも、シェアード・ディシジョンメイキングにあるように拝察します。詳しくはこちらを。
参考資料*¹:令和6年度診療報酬改定の概要説明資料 P.26
引用・参考資料*²:中山健夫『これから始める! シェアード・ディシジョンメイキング 新しい医療のコミュニケーション』(日本医事新報社)
参考資料*³:中山和弘著『患者中心の意思決定支援―納得して決めるためのケア』(中央法規出版)