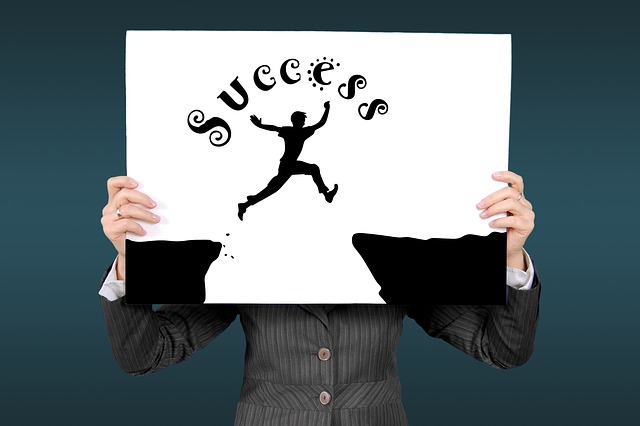本ページはプロモーションが含まれています。
自己効力感を高めて
病気に前向きに立ち向かう
臨床で日々患者と向き合っていると、「自分はきっとできる」と信じて前向きの気持ちで治療に取り組んでいる方と、「自分には無理かもしれない」「どうせできない」などと半ば諦めの姿勢で治療を受けている方とでは、回復の度合いが違うことを実感させられる――。
こんな主旨の話を、これまでの取材で何人もの医師から聞いてきました。そしてこの話の後は、必ずと言っていいほど、こんなふうに続くのです。
「ですから看護師さんには、患者さんが自分はできるんだというポジティブなセルフイメージで病気や治療に立ち向かえるようにかかわっていただきたいと、書いておいてください」
すでにお気づきでしょう。このところ看護はもちろんですが広く臨床においてその重要性が見直されている、患者の「自己効力感」、いわゆる「セルフエフィカシー(Self-efficacy)」を高めるアプローチに関する話を書いてみたいと思います。
自己効力感が高い状態と
自己効力感が低い状態
「自己効力感」とは、カナダの認知心理学者で、アメリカ西海岸にあるスタンフォード大学で長年教授を務められたアルバート・バンジューラ(Bandura.A.)博士により、1990年代に提唱された概念です。
長い人生の過程において、人は皆、実にさまざまな課題に直面するものです。目の前にある課題の解決に向けて行動を起こそうとするとき、誰もがいったんは立ち止まり、「自分にできるだろうか」と自問します。
このとき、「大丈夫、自分はできる」とポジティブに考えることができれば、課題の解決に必要な行動を即座に起こすことでしょう。ところが「どうも自分にはできそうもない」などとネガティブに受け止めてしまうと、行動に移すことを躊躇してしまいます。
このうち前者の、「自分はできる」と自分を信じて実際の行動に移すことのできる力、簡単に言えば「やる気」を、バンジューラ博士は「自己効力感」という表現で説明しているのです。
同じ課題に直面しても、自己効力感が高い状態にあれば容易に行動を起こすことができます。逆に自己効力感が低い状態にあると、「自分には無理だ」「自分にはそれをやる能力がない」などと考え、行動を起こすことに消極的になってしまう、という考え方です。
患者の自己効力感を把握し
より高めるアプローチを
急性期、慢性期の別なく、病気の治療や症状の改善・緩和に患者が自ら主体的に向き合うことができるかどうかは、この自己効力感に大きく影響されます。自己効力感が高ければ高いほど、患者はポジティブな気持ちで治療やセルフケアに積極的に取り組みます。結果として、病気も快方に向かう確率が高くなります。
そこで、まずはその時点での患者の自己効力感がどのようなレベルにあるのかを把握し、そのレベルを少しでも高めることができるようにアプローチして、治療やセルフケア効果を上げる方向にもっていこうというわけです。
自己効力感の測定方法
自己効力感を把握する尺度としては、大阪大学大学院の平井啓准教授(人間科学研究科・公認心理師)らの研究チームが考案した「SEAC」として知られるアンケート用紙、「病気に対する効力感尺度」*¹がよく用いられているようです。
このアンケート用紙には、以下のような質問が全部で18項目並んでいます。
- 食べたいと思う量の食事をとることができる
- 怒りを表に出すことができる
- イライラせずに1日を過ごすことができる
- 夜は眠ることができる
それぞれの質問に、「できる」と「完全な自信がある」場合を100点、「まったく自信がない」場合を0点とし、その間を10点刻み、11段階で点数が配分されています。
被験者は各質問ごとに、その時点でぴったりくる点数に〇印を付けていき、その点数の変動から、自己効力感の変動をみていくというものです。
自己効力感をより高める
4つの方法
では、把握した自己効力感をより高めるためにはどうすればいいのでしょうか。この問いに答えてバンジューラ博士は、以下の4つの方法をあげています。
- 達成体験
大きすぎない、挑戦すれば達成できそうな目標を設定して「できた !」という達成感を積み上げていく - 代理経験
憧れている人などがうまくやっている様子を観察して、「自分にもできそうだ」「できるかもしれない」という感覚をもつ - 言語的説得
達成できていることを「こんなことができるようになってすごいですね」などと言葉で評価し、自分にもやり遂げる能力が十分あると自らに自信を与える - 生理・情動的説得
過去にうまくできた時に体験した高揚感を思い出して、「できないという思い込み」を払拭させる
「笑い」が自己効力感を高める!?
「笑い」が自己免疫力を高めることは内外の研究により科学的に確認されています。加えて、笑いによるポジティブな感情が自己効力感にもプラスに働き、高めることができる可能性があるとする研究結果が、報告されています。
これは大阪国際がんセンターの研究チームが取り組んでいる研究です。関心のある方は、こちらで紹介していますので読んでみてください。
自己肯定感より
自己効力感を大切に
ところで、「自己効力感」とよく混同されやすい概念として「自己肯定感」があります。同義語のようにとらえられがちですが、この2つには大きな違いがあります。
まず「自己効力感」は、過去の自分の実績などから「自分はできる」と自らを信じて実際に行動を起こすことができる力を言います。この自己効力感が低いと、「どうも自分にはできそうにない」などと、行動の結果に対して弱気になり、なかなか行動に移すことができない傾向があります。
これに対し「自己肯定感」は、「できる」「できない」にかかわらず、とにもかくにも自分の存在自体を肯定する力のこと。「自尊心」とか「優越感」と言ってもいいでしょうか。
両者の違いについて、脳科学者の毛内拡(もうない ひろむ)氏は著書『「気の持ちよう」の脳科学 』(筑摩書房) のなかで、「自己肯定感は他人や過去の自分と比べることで得られる感覚のため、劣等感を強める恐れがある。それよりも『自分はこれをやった』という『自己効力感』を大切にしたほうがいい」と記しています。この本は、おもしろく読むことができますから、是非一度読んでみてください。
なお、自己効力感、いわゆるセルフエフィカシーの基本的なこと、および看護現場での活用法を具体的に知りたいという方には、少し前に刊行されたものですが、『セルフ・エフィカシーの臨床心理学』(北王路書房)、あるいは近刊の『自己効力感とレジリエンスを高める看護の実践
』(学研メディカル秀潤社)をおすすめします。
参考資料*¹: 病気に対する効力感尺度