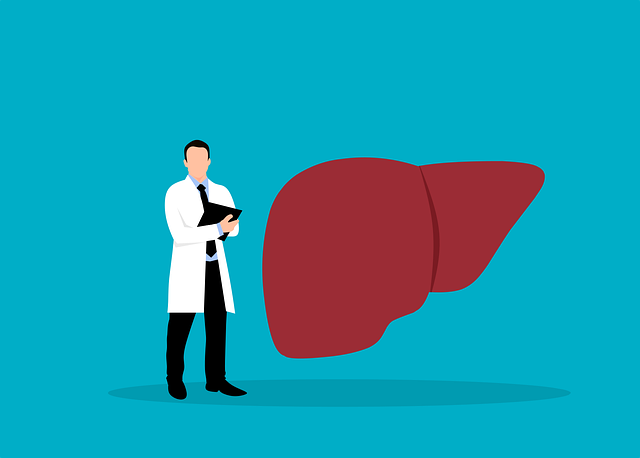肝炎患者のリハビリに
筋肉を鍛える「肝炎体操」
肝炎など肝疾患の患者に対する生活指導では、栄養療法と並び運動療法が特に重視されています。このうち運動療法については、肝炎の急性期はもちろんですが肝硬変のような慢性期にある肝疾患患者にも、「肝臓への血流量を維持するため」などとして、とかく「安静」の必要性を強調しがちではないでしょうか。
確かにきつすぎる運動はすすめられません。しかし、筋肉を収縮させる際のエネルギーに酸素を使う、いわゆる「有酸素運動」であれば、運動負荷がかかりすぎる心配はなく、むしろ体の機能維持、そして機能の回復にもプラスの効果があることが、いくつかの研究により確認されています。
そこで、体力が落ちた肝炎や肝臓がんの患者のリハビリテーションプログラムとして、大きな筋肉を鍛える「肝炎体操(へパトサイズ)」が肝臓専門医らにより開発され、肝疾患の有無に関係なく、広く一般の高齢者にも健康寿命を延ばす運動として注目を集めています。
入院中はもちろん、退院後も自宅などで誰でも簡単にできるこの「肝炎体操」を、肝硬変のような慢性肝疾患や肝臓がんの患者に運動療法として取り入れることを、まずは主治医に提案してみてはいかがでしょうか。
第二の肝臓,骨格筋に
肝機能を補完する働き
「肝炎体操」は、久留米大学の川口巧(かわぐち たくみ)教授(肝臓専門医)と橋田竜騎(はしだ りゅうき)講師(整形外科医)によって開発されたプログラムで、「消化器体操」あるいは「10分体操」と呼ばれることもあります。
安静を重視して運動量の少ない生活を続けていると、全身の筋肉は委縮してしまいます。筋肉のなかでも骨格筋は、「第二の肝臓」と呼ばれるように肝臓とよく似た役割をして、機能低下に陥った肝機能を補う働きがあることはご承知と思います。
筋肉はたんぱく質だけでなくエネルギーの貯蔵庫でもありますから、肝臓に貯蔵してあるエネルギーが不足しても、筋肉が代わりに供給してくれるのです。
また、肝機能が低下すると、老廃物であるアンモニアの処理能力が低下して血中アンモニア濃度が上昇し、最悪の場合、意識障害を伴う「肝性脳症」に陥ることがあります。
幸いなことに、アンモニアは筋肉でも分解処理されますから、肝炎体操をして筋肉を鍛えておけば、筋肉が肝臓のアンモニア代謝を補完してくれるため、肝性脳症を予防、あるいは症状緩和の効果が期待できるというわけです。
肝炎体操で
背中や臀部、脚の筋肉を鍛える
肝炎体操は、腕を前後に大きく振りながら、その場でリズミカルに20回を目標に足踏みをする「ウォーミングアップ」からスタートします。続いて以下に紹介する4つの運動を行い、最後にこむら返りの予防として、片足それぞれ20秒ずつ「ふくらはぎのストレッチ」を行って終了、というプログラムになっています。
- 背中の筋肉を鍛える「お辞儀の動作」を10回を目標に
下を向かずに、目線を前に置いたまま、腕を胸の前で交差し、猫背にならないように背筋をピンと伸ばした状態で上半身をゆっくり前に倒す - 「タオルを使って」肩や背中の筋肉を鍛える運動を10回を目標に
タオルを頭上で持ち、肘を曲げて背中側に下ろし、肩甲骨を内側に引き寄せる - 「スクワット」でお尻や腰、脚の筋肉を鍛える運動を10回を目標に
背筋を伸ばしお尻を後ろに突き出しながら膝を曲げる - 「つま先立ち」で足首を引き締め、脚の筋肉を鍛える運動を10~20回を目標に
立った姿勢でイスの背をつかみ、両足の踵(かかと)をまっすぐ上げ下げする
最初から目標と決められた回数をクリアしようとして無理をすると、捻挫などを起こしてしまい長続きしません。毎日続けることを優先して、できる回数から始め、楽にできるようになったら目標回数を反復するように指導するといいでしょう。
プログラムの所要時間は全部で10分から15分程度ですから、気が向いたときにやろうと思えばいつでもできます。
肝炎体操の詳しい方法は、国立国際医療研究センター・肝炎情報センターのWEBサイト*¹にて、動画(youTube)、スライド(静止画像)、PDF版の3タイプで紹介されています。
肝炎体操は
脂肪肝の改善効果も
肝炎体操には、脂肪肝を効率よく改善する効果も期待できることが確認されています。
肝炎体操のような筋肉トレーニングを行うと、「マイオカイン」と総称されるいくつかのホルモン物質が筋肉から分泌されます。このマイオカインが血液を介して肝臓に到達すると、肝臓の細胞が中性脂肪をエネルギーに変える働きが促進され、結果として中性脂肪が減り、脂肪肝が改善されるというメカニズムです。
リハビリの適否は主治医と相談
なお、肝炎、肝がん、脂肪肝のいずれの患者でも、リハビリテーションの適否は、主治医と相談して判断する必要があることをお忘れなく。
また、肝炎患者の身近な相談役として「肝炎医療コーディネーター(肝炎コーディネーター)」の活動に期待が寄せられていますが、肝炎医療コーディネーターについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。