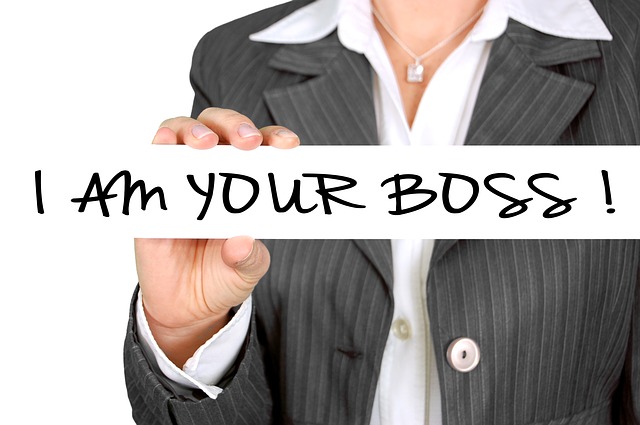本ページはプロモーションが含まれています。
医師が看護師から
セクハラやパワハラを!?
特定の人やグルーブからいじめられたり、無視されたり、いわゆる「パワハラ」や「セクハラ」を受けたり……と、職場におけるハラスメントが後を絶たないようです。ニュース報道でみる限り、むしろこのところ増加傾向にあるようにみえます。
医療現場も例外ではないようです。病院で、あるいは地域ケアの現場でも多くの看護職の方々が、上司や同僚から、あるいは医師や医療チームの仲間から、さらに深刻なことに患者や家族などからハラスメント被害に遭い、最悪のケースでは離職というなんとも残念な手段を取らざるを得ない状況に追い込まれる、といった話も少なからず耳にします。
加えて、これはちょっと意外に思えて驚いてしまったのですが、全国の病院に勤務する医師(男女)を対象に2018年に行われたある調査で、2割を超える医師が「看護師からセクハラやパワハラを受けた経験がある」と答えているのです。
ところが、この「セクハラを受けた」「パワハラを受けた」という答えの具体的な内容を見てみると、「えっ、これがセクハラになるの?」「こんなことをパワハラと受け止めてしまうの?」といったものがほとんどなのです。
どうもそこには、相手の感情や思いを受け止め、傾聴、共感し、信頼関係を築きながら問題解決に努めるという、医療に携わる人に求められる最も基本的なこと、簡単に言えば「対話」というものが成り立っていないように思えるのですが、いかがでしょうか。
そこに対話が成立していれば、
ハラスメントは起きていない?
前述の、看護師から医師に対するセクハラやパワハラに関する調査は、日本で最大級とされる医療従事者専用の医療情報サイト「m3.com」の編集部が、2018年10月に実施したものです*¹。
いくつかの質問に、全国の医師503人(勤務医252人、開業医251人)から寄せられた回答が紹介されています。この回答のなかで、たとえば「セクハラ」の実例として、「デートに執拗に誘われた」「プライベートのことや結婚についてしつこく聞かれた」「(まったく好みのタイプの女性ではなかったのに)じっと胸を見ていた、気があるんじゃないかと言いふらされた」とあります。
また「パワハラ」としては、「主任が中心となって看護師全員から業務に非協力的にふるまわれた」「看護師から圧力を受けて手術に入れなくなった」「研修医時代に大学病院でお局看護師にいびられた」などが挙げられています*。
職場におけるパワーハラスメントの定義
セクハラにしてもパワハラにしても、その定義は諸々ありますが、たとえば厚生労働省は「職場におけるパワーハラスメント」を次のように定義しています。
この定義と照らし合わると、先の調査で医師等が看護師からのセクハラとかパワハラと指摘している行為は、ハラスメントに該当しないのではないでしょうか。
少なくとも、両者の間にきちんとした「対話」が成立していたら、おそらくは不快な思いをしたり、尊厳を傷つけられたと感じたり、不安に陥るようなことにはならなかっただろうに、と思うのですが、いかがでしょうか。
患者-医療者間の紛争解決が
医療メディエーションの始まり
そこでふと思いついたのが、このところ一部の医療機関で積極的に取り入れられ、看護師をはじめとする医療スタッフ対象の研修も広く行われるようになった「医療メディエーション」の仕組み、あるいは考え方です。
医療メディエーションはもともとは、医療事故に代表されるような医療者側と患者側との間に起きたトラブルが裁判にまで発展する前に、両者間でそのトラブルを解決するための手法としてスタートしたと聞いています。
その後、たとえば患者や家族などから医療機関に寄せられる日常的なクレームレベルの問題の対応にも、医療メディエーションの仕組みが積極的に活用されるようになり、広く一般にも知られるところとなったようです。
最近では、病棟など医療現場において起こるスタッフ同士、あるいは上司と部下との間で生じるトラブルやいざこざの解決に、さらにはインフォームドコンセントの場面などでも、このメディエーションの考え方が積極的に活用されて効果をあげていると聞きます。
対話による関係構築を促す
医療メディエーターの存在が
もう10年ほど前になりますが、日本の医療界に医療メディエーションの仕組みを紹介した和田仁孝教授(早稲田大学大学院法務研究科)の講演を、取材したことがあります。
そのとき和田教授は、「対話による関係構築」という言葉を使って医療メディエーションを説明しておられたことを、非常に印象深く記憶しています。記憶をたどると、概ねこんなふうに説明しておられました。
当事者間で対話が成立すれば関係がこじれることはないのだが、その対話ができていないから関係がこじれて問題になってしまっている。そこで、当事者間の対話を促し、損なわれた信頼関係を修復して、関係を改善できるように対話を仲介する役割を担う人の存在が必要になってくるのだ、と――。
医療の現場において、この対話仲介者、あるいは対話推進者の役割を担う、いわゆる「医療メディエーター」には、ケアマインドの高い看護師さん、とりわけ患者や家族との関係という面において臨床経験の豊富なベテランの看護師さんが最も適していると思う、という話だったと、当時の取材メモの走り書きにあります。
国も診療報酬体系に
「患者サポート体制充実加算」を新設
国は2012年度の診療報酬改定で、「医療従事者と患者との対話を促進するため」として、「患者サポート体制充実加算」を新設しています(入院初日に限り70点を加算)。
この算定要件のひとつに、そのための相談窓口を設置することをあげ、その窓口に配置する職員は「医療関係団体等が実施する医療対話仲介者の養成を目的とした研修を修了していることが望ましい」としています。
このように国が推進していることもあり、医療仲介者である「医療メディエーター」を目指して日本医療メディエーター協会などが実施している研修プログラムを受講する医療スタッフ、特に看護職が年々増えていると聞きます。
ということは、対話による関係構築の手法をマスターした医療メディエーターがあなたの身近にもいる可能性があるということではないでしょうか。
仮にあなたが今、職場でのハラスメントを受けて悩んでいたら、思い切ってその医療メディエーターに相談してみてはどうでしょうか――。
患者から、あるいは医師や同僚からのハラスメント被害で悩んでいる看護師さんが少なくないと聞き、SOSのメッセージを伝えたくて、縷々書いてみました。
医療メディエーターを目指したい方
なお、自らその医療メディエーターを目指したい、あるいは医療メディエーターはともかく、日々の看護実践に対話を促進するノウハウを生かして、患者や同僚との関係の改善につなげたいという方は、コチラを参照してみてください。
参考資料*¹:看護師から医師に対するセクハラ・パワハラに関する調査